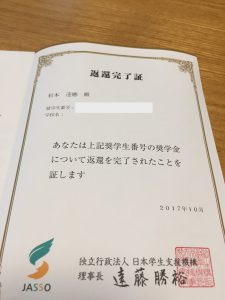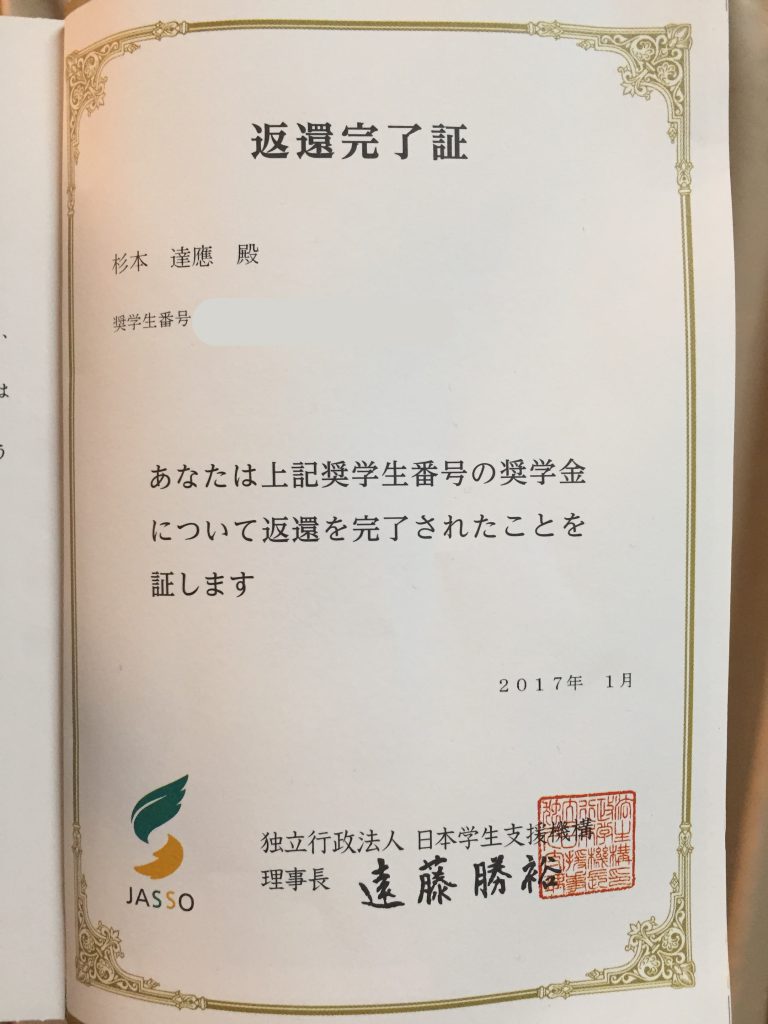これは、経済学のことはなにもわからない人間のメモです。
「地域通貨」ということばをはじめて理解したのは、IAMASでの桂英史さんの授業だった。それまで地域通貨とは、特定の地域のみで流通する通貨や商品券のようなものだろうと漠然としか理解していなかった。ところが地域通貨とは、国家が管理する貨幣とは別の体系をもった貨幣のことを指していて、そこには一定の思想性を帯びていることをはじめて知ったのだ。
いや正確には、こうした取り組みを知っていたが関心をもたなかったのだろう。なぜなら、このことを世に知らせたドキュメンタリー番組をたしかに観た記憶があるからだ。
その番組は、『エンデの遺言──根源からお金を問う』(NHK、1999年)。『はてしない物語』や『モモ』を書いたドイツの作家ミヒャエル・エンデが、「お金」について考えていて、お金を問い直す国際会議の開催を呼びかけていたという。放映当時、エンデはすでに亡くなっている。この番組では、生前のエンデに取材した音声テープを出発点に、世界のオルタナティブな通貨システムを紹介している。
放映後、番組制作者らによる同名の書籍が刊行されている。しばらく前から持っていたが、しっかり読み通したのははじめてかもしれない。
講談社
売り上げランキング: 21,708
地域通貨の思想的な始祖として、ドイツの経済学者シルビオ・ゲゼルの名があげられている。ゲゼルは通貨制度「自由貨幣」を提唱した。これは時間にともなって価値が減じる貨幣で、エイジング・マネー(aging money)とか、減価する貨幣、老化する貨幣とも呼ばれている。一般的な通貨は預ければ利息がつくが、自由貨幣はその反対で保有しつづけていると価値が下がってしまう。いわばマイナスの利子がついてしまうため、貯蓄するインセンティブがなくなる。お金が滞留せずにすばやく回りはじめるため、消費が活性化するという。
20世紀初頭の大恐慌期には、国民通貨とは別に、地域や用途が限定された補完通貨や代用通貨というのが数多く生まれていたそうだ。その後も各地で自由貨幣のコンセプトをもつ通貨の事例が紹介されている。
スタンプ貨幣は、一定期間ごとに少額のスタンプ(切手のようなもの)を裏面に貼らなければならない。スタンプを貼らなければならない日に貨幣を所有したくないので、すぐに手放すことになる。
LETSや交換リングは、プラスもマイナスも許容する、全体としてはゼロになる通帳型のシステムで、コミュニティ内の「貸し借り」を可視化する試みだといえるだろう。
本書は全体として資本主義、グローバリズム批判のイデオロギー色を帯びている。ゲゼル研究会の森野榮一による章、とくに第5章は、繰り返される金融システム批判があまりに情緒的すぎて、やや胸焼けしてしまった。
欲望か倫理か
スマホが普及した現在、自由貨幣のシステムは電子的に実装すれば、一気に姿を変えるだろう。電子化すればスタンプ貨幣を現代に甦らせることもできるだろう。スタンプ貨幣はそもそもスタンプを用意して貼りつけるのが煩雑であるし、スタンプ貼付日前後の所有者間に発生する不公平を感じる。もし連続的に減価する貨幣として実装しなおすことができれば、新たなマイナス利子のお金をつくれそうだ。交換リングも仮想市場として実装できそうだ。
あらたに作るまでもなく、現在すでに電子マネーやポイント、ビットコインをはじめとする暗号通貨など現代版の「もうひとつの通貨」が多数存在している。ただしこれらの通貨は、いずれも本書の言葉でいえば、「競争セクター」にあり、「共生セクター」には属していない。資本主義のマネーが、ひとびとの欲望を駆動力にしているように、現在の電子マネーや暗号通貨も欲望によってふくらんでいる。
本書が提唱している「もう一つの通貨」は、欲望よりも倫理に訴えかけたものだ。しかし欲望と倫理を天秤にかければ、人々はたやすく欲望に落ちるのではないか。「ふるさと納税」がその好例だ。制度の趣旨に賛同するというよりも、返礼品を目当てにしている者がほとんどだ。
自由貨幣は、減価の特性に着目するよりも、共同体に着目していることから「コミュニティ通貨」という呼び名のほうがふさわしい。しかしコミュニティ通貨は使途が制限されている。いくら流通速度がはやいとはいえ、国民通貨にくらべると流動性は低いことは大きなデメリットだ。
コミュニティの経済といえば、フリマアプリ「メルカリ」の経済圏も思い浮かぶ。メルカリの世界のなかでは、メルカリ内で有効なポイントで売買できる。ポイントは、まさに特定のコミュニティでしか通用しないコミュニティ通貨である。しかしメルカリには、共同体の意識が希薄だ。検索容易な商品のカタログは充実していて、交換リングのカタログを彷彿させる。しかし出品者の顔は見えない。ユーザは匿名であり、配送すら匿名でできてしまう。ユーザ間のコミュニケーションは、値引きや配送といった取引に関わることに限定されるようにデザインされている。
メルカリポイントは換金でき、国民通貨とほぼ等価であることも重要なポイントである。だからこそ、商売にする人があらわれ、経済圏が成長した。
コミュニティ通貨とメルカリとを比較するなんて、乱暴だという意見があるだろう。前者は共同体指向なのに対し、後者は一私企業が運営する商業的サービスでしかない。しかし普及規模の差をみれば、メルカリに学ぶべきこともあるはずだ。コミュニティ通貨がフェアトレードと同じように、「現行システムへの批判」という思想でしか対抗できないとすれば、一部の人たちにとっての不満の発散でしかなく、ひろく普及することはむずかしいのだから。
河邑厚徳・グループ現代,2000,『エンデの遺言「根源からお金を問うこと」』NHK出版.
河邑厚徳・グループ現代,2011,『エンデの遺言 ―根源からお金を問うこと』講談社.
目次
文庫版まえがき 河邑厚徳
プロローグ 「エンデの遺言」その深い衝撃 内橋克人
第1章 エンデが考えてきたこと 河邑厚徳
第2章 エンデの蔵書から見た思索のあと 村山純子
第3章 忘れられた思想家シルビオ・ゲゼル―老化するお金の理論とその実践の歩み 森野榮一
第4章 貨幣の未来が始まった 鎌中ひとみ 村山純子
第5章 お金の常識を疑う 森野榮一
エピローグ 日本でも「お金」を問い直す気運高まる 河邑厚徳
おわりに 河邑厚徳